米津玄師さんは作詞・作曲・演奏からジャケット制作まで一人でこなす天才的なアーティストです。
「パプリカ」や「Lemon」のようなヒット曲を通じ、独自の作曲法で多くのリスナーを魅了してきました。
米津玄師の作曲法〜創り出す世界観
音楽とアートが融合した独自のスタイル
米津玄師さんの作曲法は、音楽とアートが絶妙に融合した独自のスタイルが特徴です。
彼は一人で作詞、作曲、アレンジ、さらにジャケットイラストやMV制作までを手掛けることで、楽曲全体を包括的にプロデュースしています。
この手法は特に「アイネクライネ」や「Lemon」といった代表曲において顕著で、音楽そのものがアート作品として成立しています。
また、彼の作曲法には、ボーカロイド(ハチ名義)時代のバックグラウンドが生かされ、DTMによる緻密なサウンドデザインが加わることで、唯一無二の世界観を構築しています。
ストーリー性とリスナーを引き込む歌詞
彼の楽曲は、物語を紡ぐようなストーリー性の高い歌詞が特徴です。
「馬と鹿」や「loser」のような楽曲において、心情を繊細に描きながらも普遍的なテーマに触れることで、多くのリスナーの共感を呼びます。
特に「Lemon」では、“大切な人を失った悲しみ”という普遍的な感情を美しい日本語の響きで表現しており、切ないメロディと相まってその世界観に引き込まれるリスナーが続出しました。
彼の歌詞は抽象的でありながらも具体的な情景を感じさせ、聞く人それぞれが自身の経験に重ねることができる点が大きな魅力と言えます。
楽曲タイトルに込められた深い意味
彼の楽曲タイトルには、彼独自の視点や深い意味が込められています。
「パプリカ」では、子どもたちが歌いやすく親しみやすい内容ながらも、“未来を描く”という普遍的なテーマが隠されています。
一方、「馬と鹿」というタイトルには、対比や矛盾を象徴する言葉遊びの技巧が見られ、楽曲全体の雰囲気とリンクしています。
また「ピースサイン」のように、前向きなエネルギーやメッセージ性が込められているものも多く、タイトルの時点で楽曲への期待感を高める構成が魅力です。
このような徹底的に考え抜かれたタイトルが、楽曲全体の深みを演出しています。
米津玄師の作曲法〜「パプリカ」と「馬と鹿」
「パプリカ」のメロディが持つ普遍的な魅力
「パプリカ」は、明るく親しみやすいメロディが特徴で、子供から大人まで幅広い層に愛されています。
この曲は覚えやすく耳に残るメロディラインで構成され、わずかなリズムや音の変化が絶妙に重ね合わされています。
彼の作曲法では、誰もが口ずさめるようなメロディの反復が効果的に使われています。
この曲が持つ普遍的な魅力は、彼がいかに「万人に届く音楽」を意識しているかを物語っています。
「馬と鹿」に表現された独特な緊張感
ドラマ「ノーサイドゲーム」の主題歌である「馬と鹿」では、力強さや緊張感が音楽に込められています。
この曲ではスネアドラムやバスドラムが印象的に使用され、リズムによってリスナーに鼓動感と躍動感を伝えています。
さらに、静寂から爆発的なサウンドへの展開を通じて、物語性を音で表現する独特な作曲法が見え隠れします。
彼らしい歌詞の深さと相まって、楽曲全体が感情を揺さぶる一体感を生み出しています。
垣間見えるジャンルの枠を超えた挑戦
「パプリカ」と「馬と鹿」に共通するのは、ジャンルにとらわれない音楽表現への挑戦です。
「パプリカ」ではポップな要素が、「馬と鹿」ではドラマチックな要素が強調され、それぞれ異なるジャンルに位置する楽曲として成立しています。
それでいて、どちらの曲も彼独自の色が濃く反映されています。
彼独自の作曲法と美学が、ジャンルの壁を越えて多様なリスナーを惹きつける鍵となっています。
米津玄師の作曲法〜音作りへのこだわり
コード進行から生まれる予測不能な展開
彼の楽曲は予測を裏切る独特なコード進行が特徴です。
一般的なポップスでは繰り返し構造が重視されるのに対し、彼の音楽は意外性を重視しつつも、耳に心地よく響くバランスを保っています。
例えば「アイネクライネ」のサビに向かう展開では、シンプルながらも聴き手の期待を巧みに裏切るコード変化が盛り込まれています。
これにより、彼の楽曲は聴くたびに新しい発見があるような奥行きのある作品としてリスナーに受け入れられています。
DTMによる緻密なサウンドデザイン
彼の作曲法の核とも言えるのが、DTM(デスクトップミュージック)を用いた緻密なサウンドデザインです。
初期のボカロP時代から培ってきた技術を基盤に、楽器ごとのバランスやエフェクトのかけ方まで、全て自身で手掛けるのが彼のスタイルです。
「Lemon」や「パプリカ」では、繊細な音の配置やエフェクトの重ね方によって、楽曲全体に深みと立体感を与えています。
このように、音を一つ一つ丁寧に作り上げる姿勢が、曲に独自の緻密さとプロフェッショナルさを生み出しています。
打ち込み音と生音の絶妙な融合
彼の楽曲では、打ち込み音と生楽器音が絶妙に融合している点も際立っています。
「馬と鹿」では、スネアやバスドラムといった生音の質感が力強いエネルギーを与えている一方、打ち込み音が楽曲全体を鮮やかに彩っています。
このような融合は、DTMを活用しながらも生楽器の持つ温かさや臨場感を重視する彼ならではの技術と言えます。
彼はDAWのLogic Proを使用して打ち込みをしています。
生音とデジタルサウンドの境界を感じさせない彼の音作りは、ジャンルを問わず多様な表現が可能であることを証明しています。

米津玄師の作曲法〜米津サウンドの要素
日本語の美しい響きを活かすメロディー
彼の楽曲には日本語の響きを最大限に活かしたメロディーが多く使用されています。
「アイネクライネ」や「lemon」など、多くの曲において日本語が持つ柔らかさや繊細さが浮き彫りとなるメロディラインが特徴です。
彼の作曲法では言葉のイントネーションと音楽の旋律が一体化しており、それがリスナーの心に深く響きます。
このような美しい日本語を用いる手法は、日本語のリズムや響きを音楽的に解析・再構築できる彼だからこそ可能だと言えます。
共作やコラボレーションに見る音楽の幅広さ
彼は作曲家として他アーティストへの楽曲提供やコラボレーションも積極的に行っています。
「パプリカ」や「まちがいさがし」など、提供楽曲にも独自の世界観が反映され、彼の作曲法に基づいた作品で多くのアーティストに影響を与えています。
また、「ピースサイン」や「馬と鹿」では、映画やドラマのタイアップを通じて多彩なテーマに挑戦し、ジャンルにとらわれない幅広い音楽性を発揮しています。
こうした共作活動は彼が持つ柔軟な作曲スタイルと表現力豊かな音楽性を示しています。
アートワークとの一体感が生む表現力
彼の楽曲は音楽とアートワークとの緊密な結びつきが大きな魅力となっています。
彼自身が手掛けるアルバムジャケットやミュージックビデオのビジュアルは、楽曲の世界観やストーリーを深く補完します。
MV「loser」の独創的なダンスや「馬と鹿」のシンプルながらも力強いビジュアルが音楽体験をさらに引き立てます。
これにより、一つの作品がまるで総合芸術のようにリスナーへアプローチすることが可能となり、彼ならではの高い表現力を感じさせます。
米津玄師の作曲法〜これから描く未来
AI時代におけるアーティストとしての挑戦
AI技術が急速に進化し、音楽業界でもAIを活用した作曲が注目を集める中、米津さんは独自のアプローチでこの領域に挑戦する可能性を秘めていると言えます。
彼の作曲法はDTMを基盤とし緻密に構築されており、この技術的土台はAI時代においても大きな利点となります。
また、音楽だけでなくアートや映像制作も手がける彼は、AIとの協働によってより幅広い表現の可能性を追求していくことでしょう。
彼の作品に見られる独特な「米津サウンド」は人間らしい感性に根ざしており、それをAIと融合させる挑戦は新たなインスピレーションを生み出すに違いありません。
新しいジャンルやテーマへの展望
彼の楽曲にはジャンルや枠にとらわれない柔軟さがあり、それが「馬と鹿」や「パプリカ」といった多様な作品の制作へとつながっています。
この多才さから考えると、新しいジャンルやテーマに挑戦する未来も期待できます。
特に、従来以上に国際的なテーマや文化的背景を取り入れた楽曲制作を進め、さらに広いリスナー層を魅了する可能性があります。
また、新しい技術や楽器を積極的に取り入れることで、これまでにない音作りを試みることも視野に入れているでしょう。
米津玄師が提示するこれからの音楽像
彼はこれまで「ピースサイン」や「Lemon」などで鮮烈な音楽体験を提示してきましたが、これからの音楽においても独自のビジョンを持って新たな境地を切り開いていくと考えられます。
音楽がデジタル化し、リスナーの体験が多様化する時代、彼はAIやDTMを含むデジタルツールを駆使しながらも、人間が感じる「温度感」を大切にした楽曲を届けていくでしょう。
彼はDAWのLogic Proを使用して打ち込みをしています。
Logic Proは彼自身の音楽を表現するツールとなっていることでしょう。

アートワークや映像表現と音楽を緻密に組み合わせた、総合的なエンターテインメントとしての音楽が、彼のこれからの活動の中心となると予想されます。
米津玄師の作曲法〜まとめ
米津玄師さんの作曲法は、独自の世界観と多彩な表現力が魅力です。
「パプリカ」や「馬と鹿」に代表される楽曲からは、ジャンルを超えた挑戦や緻密な音作りへのこだわりが感じられます。
全てを自ら手掛けるそのスタイルは音楽界に新たな価値を提供し続けています。
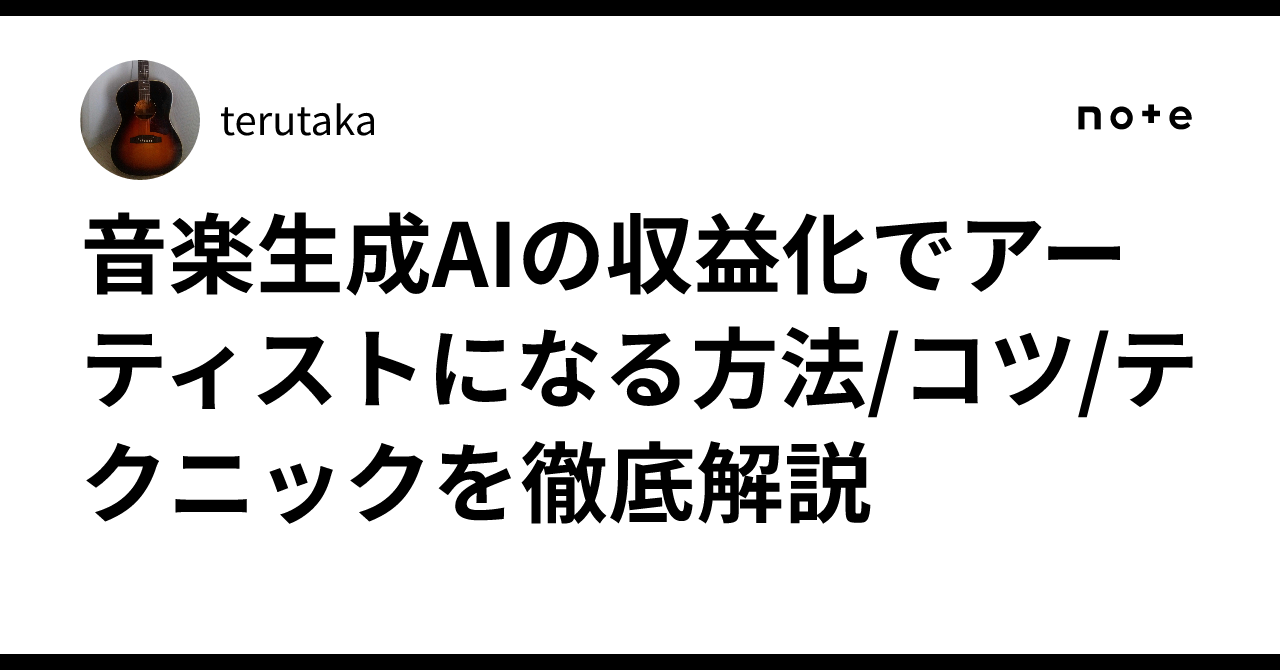

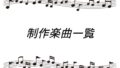

コメント